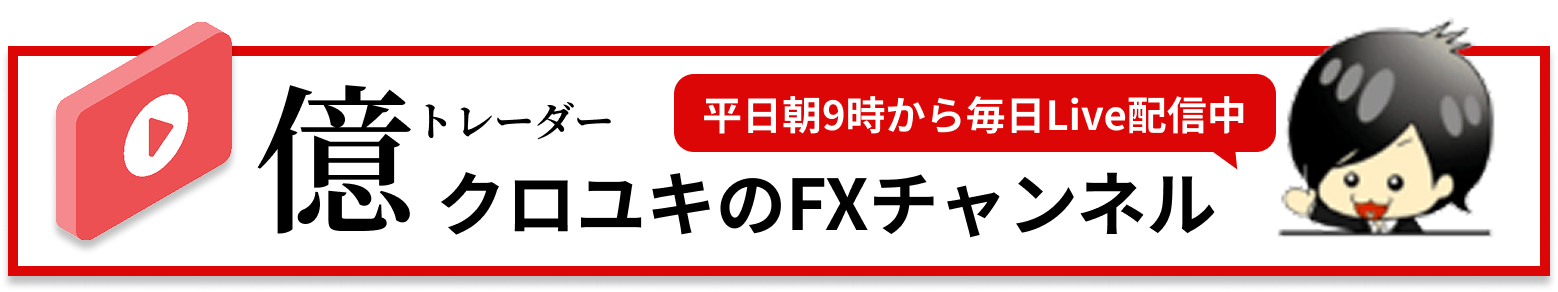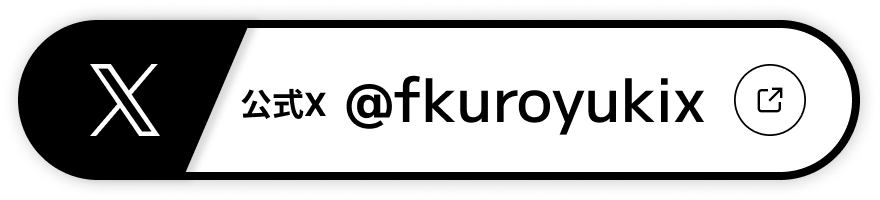結果を伸ばす近道は、個別インジケーターの寄せ集めではなく「統合された基準」を持つことです。散らかった画面は判断を遅らせ、根拠の重なりも見失いがちになります。
僕もかつては移動平均やピボット、水平線を別々に重ね、描画制限や視認性の悪化で肝心の一手を逃しました。ツールが多いほど安心だと思い込み、むしろ迷いを増やしていたわけです。
そこで取り入れたのが、押し安値と戻り高値、EMA20と200、ピボット、重要水平線、ボラティリティ、優位方向、転換アラートまでを一体化した「クロスキャ」です。基準と方向と波形が一画面で揃い、ライブでも再現しやすい判断プロセスに置き換わりました。
相場の基準が明確になれば、買いか売りか静観かの切り替えが速くなります。迷いが減り、待つべき場面と攻めるべき場面の区別もはっきりします。
過去の煩雑さを踏まえて改善してきた結果、現在の最適構成は次の通りです。
- 押し安値戻り高値の自動表示でトレンド把握を標準化
- 20EMAと200EMAに上位足20の擬似表示を併用
- デイリー週次月次年次ピボットで節目認識を多層化
- 前日当日の高安値とボラ数値で地合いを即判定
- 優位方向と重要水平線の自動抽出で迷いを排除
- トレンド転換アラートで押し割れ戻り抜けを通知
- 秒スキャの1pipsグリッドと切り番強調で精度向上
クロスキャの概要と導入方法
クロスキャの全体像と特徴

クロスキャは、複数のインジケーターを組み合わせる手間を省き、1つで相場分析を完結させる設計です。押し安値や戻り高値、EMA、ピボット、水平線といった要素を自動表示し、トレンドや優位性の判断を支援します。
従来は「EMAとピボットを別々に設定し、さらに高安値を自分で探す」といった作業が必要でしたが、クロスキャを使えばワンクリックで統合された環境を得られます。
この特徴を整理すると次の通りです。
- トレンド判断の根拠を自動で提示
- 相場の基準線や重要ラインを表示
- ボラティリティや時間帯を視覚的に把握可能
僕自身も以前は複数のインジを重ねすぎてチャートが見づらく、逆に判断を迷うことがありました。クロスキャを導入してからは、必要な情報が整理された形で一目で分かり、判断スピードが格段に上がりました。
そのため、クロスキャは「相場認識を効率化する統合ツール」として役立ちます。
平日9時のライブ配信で使い方を確認
クロスキャは単なる配布ツールではなく、毎朝9時からのライブ配信で実際の使い方を学べる点が強みです。リアルタイムの相場に対し、どのラインを根拠にエントリーするのか、どのシグナルを無視するのかといった判断過程を直接確認できます。
解説記事やマニュアルだけでは「どの場面で使えばいいか」が曖昧になりがちですが、ライブでは実戦に即した判断が見られるため、理解度が深まります。
活用のポイントは以下です。
- ライブでシグナルが出た瞬間の根拠を学ぶ
- 無駄なエントリーを避ける実例を確認できる
- 質問を投げて即座に回答を得られる環境がある
僕も最初はピボットやEMAの有効性を「本当に効くのか」と疑っていましたが、ライブで実際に機能する場面を目の当たりにして確信に変わりました。
だからこそ、クロスキャを学ぶには配信を通じて「実際にどう効くのか」を見るのが最も効果的です。
JFX口座保有者への配布条件
クロスキャは誰でも自由にダウンロードできるわけではなく、JFX口座を開設した人に限定して配布されています。この仕組みには理由があります。無制限に配布すると誤用や中途半端な理解で使われやすく、せっかくの機能が活かされないからです。
条件をまとめると次の通りです。
- JFX口座保有者限定で配布
- セミナーや解説動画で使い方をフォロー
- アップデートや改善要望を反映できる環境あり
僕自身も過去に無数の無料インジを試しましたが、配布だけでフォローがないため、結局使いこなせず終わることが多かったです。クロスキャは配布条件を絞り込むことで、サポートと実用性を両立しています。
したがって、口座を開設して導入することで「学びと実践が両立した環境」を得られるのです。
相場認識を支える主要機能
押し安値・戻り高値の自動表示
トレンドを見極める上で最も基本となるのが「押し安値」と「戻り高値」です。クロスキャではこれを自動表示することで、今が上昇相場か下降相場かを直感的に把握できます。
基準を自分で探すと、ラインの引き方にブレが出やすく「今は上昇か下降か」で迷う原因になります。自動表示があることで、判断が統一され迷いが減ります。
整理すると以下のようになります。
- 押し安値を割る→上昇トレンドの終了
- 戻り高値を超える→下降トレンドの終了

僕自身も経験がありますが、主観で「まだ上がるだろう」と思い込み、損切りを遅らせる失敗は少なくありませんでした。押し安値・戻り高値を基準にすることで、感情を排除した判断が可能になります。
このため、この機能は初心者から上級者まで「相場認識の土台」を強化する支えになります。
20EMA・200EMAと上位足20EMAの擬似表示
移動平均線は多くのトレーダーが使う王道指標です。クロスキャでは20EMAと200EMAを表示でき、さらに上位足20EMAを滑らかに再現する擬似表示機能があります。
20EMAは短期の勢いを把握するため、200EMAは相場の大局を見極めるために用いられます。この2つを組み合わせることで、方向感と相場環境を同時に確認できます。
活用イメージは次の通りです。
- 20EMAが200EMAより上→上昇基調
- 20EMAが200EMAより下→下降基調
- 上位足20EMAを下位足に表示→大局を意識した精度の高い判断
僕もかつては1分足の動きだけを見てエントリーし、すぐ逆行することが多々ありました。今は上位足20EMAを参考にすることで、全体の流れに逆らわずエントリーができます。
つまり、この機能は「短期と長期を結びつける橋渡し」となります。
デイリーから年間まで対応するピボット表示
ピボットは前日の値動きを基に算出される「相場の基準線」です。クロスキャでは日足・週足・月足・年足のピボットを切り替えて表示でき、相場の重合ポイントを見極める助けになります。
基準線がないと「買いか売りか」の判断が遅れますが、ピボットを使えばその日の出発点が明確になります。
整理すると次の通りです。
- ピボットより上で推移→買い優勢
- ピボットより下で推移→売り優勢
- 複数のピボットが重なるゾーン→強力な支持・抵抗帯
僕自身も以前はEMAやRSIだけに頼り、相場の基準が曖昧でした。その結果、安易な逆張りで損切りが増えていました。ピボットを取り入れてからは「ここは買い支え」「ここは売り圧力」と基準が明確になり、判断が安定しています。
そのため、勝てない人ほどピボットを基準線として取り入れるべきです。
トレード判断を補強する分析機能
前日・当日の高安値とボラティリティ表示
相場は日ごとに特徴が変わります。クロスキャでは「前日と当日の高値・安値」を自動表示し、さらにボラティリティを数値で確認できます。これにより「今日は大きく動く日か」「方向感が乏しい日か」を一目で判断できます。
整理すると次の通りです。
- 前日高値・安値→反発やブレイクの目安
- 当日高値・安値→直近の値動き基準
- ボラティリティ数値→相場が活発か停滞かを即座に把握
僕自身も過去には「動かない相場」に無理に入ってしまい、薄い値幅で損切りを繰り返すことがありました。ボラティリティ表示を参考にしてからは「今日は動く」「今日は待つ」と戦略を変えることができ、無駄なエントリーが減りました。
このため、この機能は「取引の選別眼」を養う上で欠かせない要素です。
優位方向の自動判定と重要水平線の自動抽出
クロスキャには、エントリーすべき方向をリアルタイムで示す機能があります。例えば「ショートのみ」と表示されれば、その時点では売りだけを狙うべきとわかります。迷いがちな初心者にとって、大きな指針となります。
さらに重要な水平線を自動抽出する機能も搭載。手作業で引くと見落としやズレが生じやすいですが、自動抽出なら信頼性が高く、抵抗や支持を見誤るリスクを減らせます。
まとめると次のような効果があります。
- 「ロング/ショートのみ」の表示→エントリー方向を明確化
- 重要水平線の自動生成→認識の統一と見落とし防止

僕も過去には、方向性を決められずに往復ビンタを食らう経験を繰り返しました。今は方向判定と水平線を活用し「待つ」「狙う」を明確に切り替えられています。
したがって、この機能は「迷いを排除し、確率の高い局面に集中」する助けとなります。
トレンド転換のアラート通知
トレードで大切なのは「流れが変わった瞬間を逃さないこと」です。クロスキャは押し安値割れや戻り高値突破を検知し、アラートで通知します。これによりチャートに張り付き続けなくても重要局面を把握できます。
利用イメージは次の通りです。
- 戻り高値を突破→加工トレンド終了の合図(緑の矢印)
- 押し安値を割れ→上昇トレンド終了の合図(赤の矢印)
- アラート設定→複数時間軸での転換を同時に監視

僕自身も昔は「気付いたらもう動いていた」という経験が多々ありました。アラート機能を使うようになってからは、転換の瞬間を見逃さず冷静に準備できます。
だからこそ、この機能は「効率的かつ精度の高いエントリータイミングの確保」に直結します。
実務を快適にする補助機能
pipsスケールと秒足スキャル用の表示
クロスキャには、現在レートからの距離を数値で表示する「pipsスケール」が搭載されています。5pips・10pips・20pipsなどの目安を視覚的に把握できるため、値幅感覚を即座につかめます。特にスキャルピングでは「どれだけ抜けるか」の判断が数秒で求められるため、この機能は非常に有効です。
さらに秒足対応の表示も備わっており、1pips刻みのグリッドや切り番ラインを自動で引いてくれます。これにより短期の攻防を逃さず捉えることができます。
整理すると次のメリットがあります。
- 値幅を数値化→伸び代を即座に判断可能
- 秒足専用表示→超短期スキャルピングにも対応
僕自身、秒足のトレードで「1〜2pipsの誤差」が勝敗を分ける経験をしました。クロスキャを使うことで視覚的な補助が増え、より冷静に判断できています。
このため、この機能は「短期決戦を支える感覚の精度」を高めてくれます。
エントリー可能時間帯の自動ライン表示
マーケットには「動く時間」と「停滞する時間」があります。クロスキャはロンドンやニューヨークのオープン時間を自動でライン表示し、主要市場が始まるタイミングを視覚的に把握できます。
活用のポイントは以下の通りです。
- 東京・ロンドン・ニューヨークの市場オープンを即座に確認
- 各市場開始から2〜3時間の「稼ぎやすい時間帯」を意識可能
- 過去の検証でも時間帯を意識した分析が容易になる
僕も以前は「なぜ同じ手法でも勝ったり負けたりするのか」に悩んでいました。後から振り返ると、勝ちやすい時間帯とそうでない時間帯が明確に存在していたのです。
要は、時間帯を意識できることでトレードの再現性が格段に上がります。
時計・タイムゾーン表示、指標リマインダー
実務を支えるもう一つの柱が「時間管理機能」です。クロスキャは時計をチャート上に表示でき、秒単位でのタイミング合わせが可能です。また検証の際には「非エントリー時間帯」をゾーンとして示すことができ、効率的に記録を進められます。
さらに「経済指標のリマインダー」機能も搭載されています。事前に設定すれば、雇用統計や政策金利などの発表を見逃す心配がありません。
まとめると次の利点があります。
- 時計・秒表示→エントリーのタイミング精度を強化
- タイムゾーン表示→検証効率を向上
- 指標リマインダー→突発的なリスクを未然に防止
僕自身も過去に、指標発表を忘れて大きな損失を出した経験があります。このリマインダーを使うようになってからは、そうした凡ミスを避けられるようになりました。
そのため、この一連の機能は「資金管理とメンタルの安定」に直結する補助となります。
サポート用インジケーター群
MAシグナル(複数本EMAと向きの一致表示)
MAシグナルは最大5本の移動平均線を同時に表示し、全ての方向が一致した時にシグナルを出します。これにより、トレンドの強さを一目で判断可能です。
例えば、20EMAと200EMAの両方が下向きなら「下降トレンドが優勢」と即座に判断できます。
活用のメリットは以下です。
- 複数EMAの方向を瞬時に統合把握
- 上位足の流れを下位足に重ねて確認可能
- ショートかロングかを迷う場面を減少
僕もかつては「MAを複数並べて見るだけ」で混乱していましたが、このインジケーターを導入してから判断がシンプルになりました。結果として、無駄な逆張りを避けられるようになっています。
黒雪ライブテクニックとテクニックプラス(フィボナッチ・水平線)
黒雪ライブテクニックはトレンド方向を自動で判定し、さらに押し目や戻りをフィボナッチで自動表示します。手作業でラインを引く手間がなく、シナリオ立案が効率化されます。
テクニックプラスでは、2点反応の水平線を自動で抽出。通貨ごとにゾーン幅や遡り本数を調整でき、実際の値動きに即したラインを生成します。さらに「ブレイク後に不要なラインを消去する機能」もあり、チャートが煩雑になりません。
この2つを組み合わせることで、
- トレンド方向の自動判定
- 押し目・戻りの候補ゾーン提示
- 水平線の自動抽出と管理
といった形で、相場分析の骨格を自動化でき、シナリオ作成を効率化できます。
RSIシグナルとボリンジャーバンド関連インジ
RSIシグナルは、設定した数値に到達した際にチャート上へ明確なサインを出します。裁量で「そろそろ売られ過ぎかな」と考える曖昧さを排除し、客観的な判断が可能になります。
ボリンジャーバンド関連のインジケーターは、通常の±2σ・±3σに加え、バンド幅の拡大を数値化してアラートも出せます。これにより「トレンド発生の初動」を見逃さずに捉えることが可能です。
活用例は次の通りです。
- RSIシグナル→過熱感の可視化で逆張りの根拠を補強
- ボリンジャーバンド拡張→ブレイク直前の値動きを数値で確認
僕も以前は「目視でバンドの広がりを判断」して失敗した経験があります。この機能で数値化されることで、自信を持って仕掛けられるようになりました。
RT6で通貨強弱と方向性を一目把握
RT6は複数通貨ペアを一覧化し、それぞれの方向性を表示します。これにより「どの通貨が強く、どの通貨が弱いか」を瞬時に把握できます。
たとえば、ユーロとポンドが上向き、ドル円が無反応であれば「ユーロやポンドの強さが際立っている」と判断可能です。スキャルピングではこの「通貨強弱の一目把握」が勝率を大きく左右します。
僕自身、過去に「単一通貨だけを見て逆方向に入ってしまう」ミスが多発していました。RT6を導入してからは、通貨間のバランスを前提にトレードできるようになり、無駄なエントリーが減少しました。
このように、これらのサポート用インジケーターは「基礎分析の効率化」と「通貨選択の最適化」を同時に実現してくれる強力なツール群です。
学習とコミュニティ活用
ライブでの実践解説と質問対応
クロスキャの特徴は、インジケーターを配布するだけでなく、平日朝9時からのライブ配信で「実際のトレード活用法」を見られる点にあります。
- リアルタイムでクロスキャをどう使うかが分かる
- トレンド判定やエントリー根拠を即時に共有
- 視聴者からの質問にその場で回答
僕自身も解説しながら実際にトレードを行うため、単なるインジ紹介に留まらず「実戦的な理解」を深められるのが大きなメリットです。ライブに参加することで、自分の判断と比較しながらスキルを磨けます。
セミナー開催や追加機能要望のフィードバック
JFX口座を持つユーザーは、定期的に行われるセミナーへ参加できます。ここではクロスキャの活用法に加え、リアルイベントでの交流や直接のフィードバック機会が提供されます。
特に好評なのが「追加機能の要望受付」です。ユーザーからの声が反映され、実際にアップデートとして実装されるケースもあります。
この仕組みにより、クロスキャは「配布されたままのツール」ではなく、利用者と共に進化し続けるインジケーターとなっています。
X(旧Twitter)やブログでの情報発信
クロスキャに関する最新情報や、日々のトレードの様子はX(旧Twitter)やブログを通じて発信されています。
- ライブ配信の告知やリアルトレードの共有
- 新しい機能やアップデートの速報
- 学習に役立つ相場解説やノウハウ
僕自身もSNSを通じてユーザーとつながり、リアルタイムでの情報交換を大切にしています。こうした継続的な発信によって、単にインジを使うだけでなく「学び続ける環境」が整えられているのです。
したがって、クロスキャは単なるツールにとどまらず、ライブやSNS、セミナーを通じて「学習と成長を支援するコミュニティ」として機能しています。
まとめ
クロスキャは、多くのトレーダーが求めていた機能を一つに統合した強力なインジケーターです。
押し安値や戻り高値、EMAやピボット、さらにはエントリー方向やトレンド転換アラートまで搭載されており、相場認識と実践の両面を強力にサポートします。
特に注目すべきポイントは以下の通りです。
- トレンドの基準線を明確化する押し安値・戻り高値の自動表示
- EMAやピボットを組み合わせた多角的な相場分析
- 前日・当日の高安値やボラティリティによる相場状況の可視化
- 優位性の高いエントリー方向や重要水平線の自動抽出
- ライブ配信やセミナーを通じた実践的な学習環境
僕自身も使い続ける中で、「基準線があることで判断が安定する」ことを実感しています。ツール単体に依存するのではなく、シナリオ作成や相場観と組み合わせることで真価を発揮します。
結論として、クロスキャは単なるインジではなく「学びと成長を後押しする環境」を提供するものです。相場の軸をまだ持てていない方ほど、ぜひ取り入れてみる価値があります。