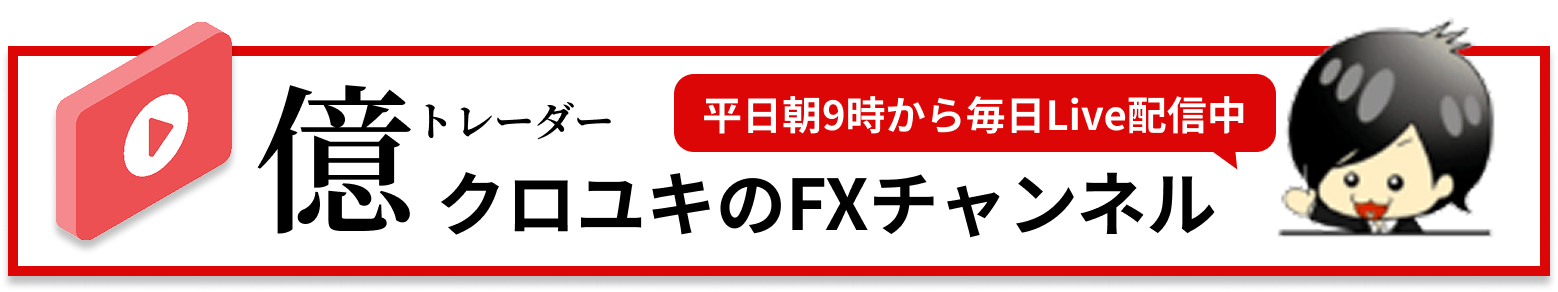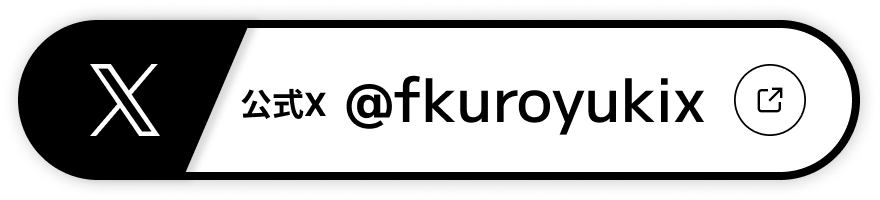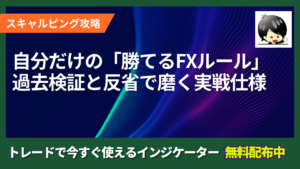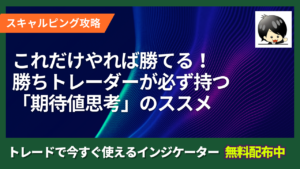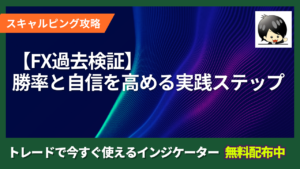僕が勝ち続けられている理由は、エントリー前のルーティンにあります。相場は不確実性が高く、その場の感覚で入ると一瞬で感情に振り回されます。
過去の僕も、指標を見落として急落に巻き込まれたり、シナリオを作らずに入って後悔したりしました。その経験から気付いたのは「勝てるトレーダーほど、例外なく毎回同じ準備を繰り返している」という事実です。
僕自身も、経済指標のチェックから環境認識、シナリオ設計までを必ず実行しています。この流れを守ることで、不要なエントリーを避け、本当に勝負すべき場面だけに集中できます。
今回お伝えするのは、僕が日々徹底している実際のルーティンです。同じ手順を取り入れるだけで、トレードの安定感は大きく変わっていくはずです。
僕がトレード前に必ず行っているルーティンは、大きく整理すると次の通りです。
- 経済指標と要人発言の事前確認を習慣化
- 休場情報を把握しボラとテクニカルの効き目を予測
- X(旧Twitter)で速報とリークを一次対応
- 信頼できる発信元のみをフォローしノイズ排除
- 月足から15分へ落とす環境認識でライン抽出
- 事前シナリオ外は一切手を出さずに待機
- 朝夕でラインを更新しアラートで機会を逃さない
トレード前のルーティンが必要な理由
ルーティンの意味とトレードへの応用
トレードにおけるルーティンとは、エントリー前に毎回繰り返す確認作業のことです。スポーツ選手が試合前に決まった動作を行うように、僕も相場に入る前に一定の流れを守ります。このルーティンがあることで、感情に流されず、冷静に判断できるようになります。
特にFXは、ちょっとした油断が損失につながります。そのため、ルーティンは単なる「習慣」ではなく、リスク管理の仕組みと捉える必要があります。
実際に僕が意識しているのは以下のような点です。
- その日の重要イベントを必ず確認する
- チャートに注意点を残して忘れない仕組みを作る
- 上位足から順番に環境認識を行う
- エントリー条件を事前に定め、即断せずに従う
このように、ルーティンを設けることで一貫した判断が可能になります。逆に、毎回やり方が変わると迷いが生じ、エントリー根拠もぶれてしまいます。
結局のところ、トレードは「準備で7割決まる」と言っても過言ではありません。だからこそ、僕はルーティンを単なる習慣ではなく勝ち続けるための武器として位置づけています。
経済指標と要人発言を確認する重要性
トレード前に必ず行うべきことの一つが、経済指標と要人発言の確認です。これは全てのトレーダーにとって必須であり、怠ると大きな損失を招く原因になります。
例えば、日銀の政策金利や米雇用統計の発表時は、チャートが予想以上に急変動します。事前に把握していれば、危険な時間帯はエントリーを避けることができます。逆に、知らずにポジションを持っていると、テクニカルを無視した動きに振り回されてしまうでしょう。
僕は忘れない工夫として、次のように仕組み化しています。
- その日の重要指標をチャート上に書き込む
- 休場情報も併せて確認し、ボラティリティ低下を想定する
- 複数のサイトを併用して誤記や抜け漏れを防ぐ
こうした確認を徹底するだけで、余計なリスクを避けられます。事前に把握していれば「この時間帯は様子見しよう」と判断できますし、エントリーの選択肢もより精緻になります。
重要なのは、自分を過信しないことです。忘れない仕組みを作り、毎回の確認をルーティンに落とし込むことが、安定した成績につながるのです。
情報収集とファンダメンタルズ確認
指標と休場情報を複数ソースでチェックする
トレード前は、経済指標と休場情報を複数の情報源で突き合わせるのが基本です。単一サイトに依存すると、誤記や更新遅延で重要情報を取り逃すおそれがあります。
僕はインベスティングのカレンダーを軸に、他サイトで時刻や内容のズレを確認する運用です。媒体によって差異が出るため、二重チェックを前提にしています。
手順は次のとおりです。
- 経済指標カレンダーを2サイト以上で比較
- 当日の主要国の休場を把握
- 注意時間帯をチャートにマーキング
休場日には流動性が落ち、狙った値動きが出にくい場面が増えがちです。米国や欧州が休みのケースではボラティリティが極端に低下し、テクニカルの効きも鈍化します。通常時と同じ期待値でエントリーすれば、思わぬ損失に直結しかねません。
だからこそ、複数ソースで照合し、あらかじめ「今日は動きにくい日だ」と見立てを持っておくことが肝心です。
X(旧Twitter)で速報とリーク情報を取得する
経済指標のように予定されているイベントは事前に確認できますが、突発的なニュースや要人発言は別です。こうした不意の情報は、X(旧Twitter)が最速で流れることが多く、僕にとって欠かせない情報源になっています。
特に最近は日銀やFRB関係者のリークが相場を大きく動かすケースも目立ちます。公式発表前に報道が走ることもあり、その第一報をつかむにはXが最も適しています。
僕が実践している活用法は以下の通りです。
- 経済報道機関や証券会社の公式アカウントをフォローする
- 市場関係者がシェアする速報をリアルタイムで確認する
- 不確かな情報は即座に鵜呑みにせず、複数の発信元で裏付ける
一次情報を直接追える人は英語のニュースを確認しても良いですが、僕自身は英語が得意ではありません。だからこそ、Xを経由して速報を効率よく把握するようにしています。
予定されていない情報が動意づけになる時代だからこそ、Xのスピードは強力な武器になります。
信頼できるアカウントのみをフォローするポイント
Xを活用する際に最も注意すべきなのは、情報の信頼性です。誰でも投稿できる場だからこそ、誤報や主観的なコメントに振り回されるリスクが常に存在します。
僕が重視しているのは「信頼できるアカウントだけをフォローする」という一点です。具体的には、以下のような基準でアカウントを選別しています。
- 証券会社や大手報道機関など、誤報リスクを極力避ける立場にある発信元
- 発言に独自の解釈を混ぜず、事実のみを端的に伝える媒体
- 市場全体をカバーしており、大きな値動きに必ず反応する情報源
一方で、個人トレーダーの見解中心の投稿は参考程度にとどめています。なぜなら、個人の意見は必ず主観が入るため、情報そのものよりも解釈色が強くなりがちだからです。
僕自身もリストを作成し、必要な情報だけが流れる環境を整えています。こうすることで、ノイズを大幅に減らし、冷静な判断を維持できるようになりました。
結局のところ、Xはスピードが最大の利点ですが、それを活かすには「誰から情報を得るか」が全てです。
相場分析と環境認識の手順
月足と週足で重要な抵抗帯を把握する
相場分析は必ず上位足から始めます。理由は、大きな時間軸で意識されるラインこそ、多くの投資家が注目する水準だからです。

僕はまず月足を確認し、過去の高値や安値にラインを引きます。例えばドル円なら、過去の介入ポイントや2001年の高値水準などが該当します。これらは数十年単位で意識されるため、直近の値動きでも強い抵抗として機能します。
次に週足で細かい抵抗帯を見ます。特に前回の反発ポイントや心理的なキリ番水準は週足で意識されやすく、相場が一度止まる可能性が高いです。
確認ポイントは次の通りです。
- 月足で歴史的な高値安値を線引きする
- 週足で直近の反発ゾーンを特定する
- 強いラインはテキストやマークで残す
月足と週足の抵抗帯を把握しておけば、短期足でどんなに強いシグナルが出ても「逆らうべきでない場面」が事前に見えてきます。
日足と4時間足で反発ゾーンを確認する
月足や週足で全体像を把握したら、次は日足と4時間足で精度を高めていきます。これにより、エントリー候補のゾーンがより具体的に見えてきます。
日足では、前回の高値や安値を基準に「どこで一旦反発しやすいか」を探します。大きなトレンドに沿った押し目や戻り売りポイントを想定できるのも日足の強みです。
4時間足では、反発がゾーンとして広がるケースを想定します。一本の水平線ではなく、複数の足が意識する帯状の価格帯を「ゾーン」として捉えることで、精度の高い待ちが可能になります。
僕が実践している流れは以下の通りです。
- 日足で前回の高値・安値をライン化する
- 4時間足で反発ゾーンを抽出する
- 必要に応じてゾーンを広く設定し、柔軟に対応する
こうして複数の時間軸でラインを重ねると、「ここで待つしかない」というポイントが絞り込まれていきます。
1時間足と15分足で押し目と戻りの候補を探す
環境認識の仕上げは、1時間足と15分足で具体的なエントリーポイントを探す作業です。この段階でようやく実際のトレードに直結する押し目買い・戻り売り候補が見えてきます。
1時間足では、トレンドの起点や押し安値・戻り高値を確認します。ここを割るかどうかでトレンドの継続か転換かを判断できるため、方向性を測る基準になります。
15分足では、より具体的な候補を絞ります。直近の高値や安値、ダブルボトムやネックラインなど、細かい反発ポイントを明確にしていきます。

僕が意識しているチェックポイントは次の通りです。
- 1時間足でトレンドの起点を確認する
- 15分足で押し目や戻り候補を抽出する
- 条件を満たすまでは絶対にエントリーしない
こうすることで「どこでなら入っていいか」がはっきりし、無駄なエントリーを排除できます。
トレンドラインや水平線でシナリオを固める
環境認識の最後は、トレンドラインや水平線を引き、具体的なシナリオを固めることです。これは「準備がすべて」と言われる理由そのもので、相場に入る前に勝負の設計図を作る段階です。
水平線では、各時間軸で抽出した抵抗帯や反発ポイントを整理します。トレンドラインでは、継続か転換かの判断基準を明確にできます。チャンネルラインを併用すれば、値動きのレンジ幅も想定できます。
僕が意識しているルールは以下の通りです。
- 水平線は「ここでしか戦わない」場所に絞る
- トレンドラインやチャンネルを重ね、根拠を強化する
- ライン付近までは一切触らず、アラートを設定して待つ
この段階でシナリオを完成させておくと、相場が動いても感情に流されません。冷静な時に作ったシナリオ通りに実行するだけなので、余計な迷いを排除できます。
シナリオ設計とエントリー条件の決定
押し目買いと戻り売りを事前に想定する
トレードの軸は「押し目買い」と「戻り売り」の二つに集約されます。だからこそ、事前にどの水準で買い、どこで売るかをシナリオ化することが重要です。
上昇トレンドが続いているなら、狙うのは押し目買いです。一方、前回の高値付近に到達した場面では戻り売りを想定します。この2つを切り替えるだけで、無駄なエントリーが大きく減ります。
僕は以下のような流れで考えています。
- 上位足が上昇なら、下位足は押し目買い狙い
- 前回高値に接近したら、短期で戻り売りを検討
- トレンド方向と反発候補を常にセットで見る
事前に想定を持たずに相場を見ていると、値動きに流されて感情的なエントリーをしてしまいます。しかし、シナリオがあれば「ここに来るまでは何もしない」と決められるため、余計な行動を防げます。
ダブルボトムや三尊などの形で待つ技術
シナリオを立てたら、次はエントリーのトリガーを明確にします。僕が重視するのは、チャートパターンを使って「待つ」技術を徹底することです。
具体的には、以下のような形を狙います。
- ダブルボトムのネックライン回帰で押し目買い
- 三尊の右肩形成で戻り売り
- トレンドラインのブレイク後リテストでエントリー
こうした再現性の高い形を待つことで、エントリーの精度が格段に上がります。逆に、形が出ていないのに飛び乗るのは感情的な行動になりがちです。
例えば、僕は5分足や1分足をトリガーに使うことがありますが、それは上位足のシナリオと整合している時だけです。全体が上昇トレンドなら、短期のダブルボトムを利用して素直にロングを狙います。
このように「形が出るまで待つ」と決めておくだけで、無駄な負けを避けることができます。
普段使わない指標や根拠を排除する重要性
エントリー直前になると、人は普段使わない情報に目移りしやすくなります。「移動平均線で抑えられている気がする」といった思いつきが、シナリオを崩す原因になるのです。
僕自身も過去に、普段見ていないテクニカルを急に根拠にしてしまい、失敗したことがありました。こうしたにわか判断は一貫性を壊し、勝率を大きく下げます。
だからこそ、ルールは明確に決めています。
- 普段使わないインジケーターは根拠にしない
- シナリオにない要素は一切採用しない
- 判断材料は事前に決めたラインと形だけに絞る
このように制約を設けると、余計な迷いが入り込まなくなります。実際、僕はルーティン化してから、根拠のぶれによる損失がほとんど消えました。
結局のところ、シナリオ通りに徹底できるかどうかが勝敗を分けます。
普段の分析で使っていない根拠を排除することは、安定して勝ち続けるための必須条件と言えるでしょう。
日内でのルーティンの見直し
朝と夕方に環境認識を更新する
相場は一日の中でも流れが変わります。だから僕は、朝と夕方の二回は必ず環境認識をやり直すようにしています。朝に立てたシナリオだけでは、日中の値動きによってラインがずれることがあるからです。
特に注意しているのは以下の点です。
- 午前中に形成された新しい高値や安値をチェックする
- 日中の流れで効き目がなくなったラインを削除する
- 新しいトレンドラインやゾーンを追加して修正する
これを怠ると、朝の段階では有効だった分析が無意味になりかねません。例えば、午前中に短期的なトレンドが発生すると、朝の押し目候補が届かないまま上昇してしまうことがあります。そこで夕方に再度確認し直すことで、その日の夜に備えた精度の高い準備ができます。
結局、相場は生き物のように動き続けます。一度引いたラインに固執せず、柔軟に更新することが安定したトレードにつながるのです。
アラートを活用して機会を逃さない
ラインを引いただけでは、チャンスを逃すことがあります。僕は必ずアラートを設定し、価格が近づいた時に自動で通知が来るようにしています。これによって、無駄にチャートを眺め続ける必要がなくなるでしょう。
アラートの置き方は次のようにしています。
- 狙っているラインの手前に設定して準備時間を確保する
- 重要度の高いラインには複数のアラートを設置する
- 不要になったらすぐ削除し、画面を整理する
例えば、反転候補の少し上にアラートを置いておけば、通知を受け取った時点で改めてチャートを確認できます。その際にシナリオ通りの形が出ていれば、冷静にエントリーの判断が可能です。
一方、アラートを使わずに常にチャートを監視していると、無駄なエントリーに手を出しやすくなります。「今動いているから入りたい」という衝動を避けるためにも、アラート管理は非常に有効です。
つまり、アラートは効率を高めるだけでなく、余計なトレードを防ぐためのメンタル管理にもつながります。
準備がトレード成績を左右する
エントリー前の分析と準備が勝敗を決める
トレードはエントリーしてから勝ち負けが決まるわけではありません。実際には、その前段階の分析と準備で結果の大部分が決まっています。
僕が意識している流れは次の通りです。
- 経済指標と要人発言を必ず確認する
- 月足から15分足まで順に環境認識を行う
- 水平線やトレンドラインを引き、戦う場所を決める
- 条件を満たしたときだけエントリーする
こうした準備を抜きにエントリーすると、値動きに振り回されて「根拠のない勝負」になりがちです。逆に、準備を徹底していれば「この場面が来たら入る」と冷静に判断でき、余計な迷いを排除できます。
僕自身も、準備を怠った時ほどエントリー後に不安が残り、途中で利確や損切りを迷ってしまいました。しかし、事前に想定を固めておけば、その後はシナリオをなぞるだけで済みます。
つまり、エントリー前にどれだけ冷静に準備を整えられるかが、最終的な勝率を左右するのです。
日々の積み重ねが安定した成績につながる
一度の大きな勝ちよりも、日々のルーティンを積み重ねることが安定した成績を生みます。準備を繰り返すことで分析の精度が上がり、相場の変化にも柔軟に対応できるようになるからです。
僕が続けている習慣は以下の通りです。
- 毎日同じ順序で分析を繰り返す
- シナリオ外では絶対に手を出さない
- 結果よりも準備の質に意識を向ける
こうした小さな積み重ねは、すぐに成果が出るわけではありません。しかし、数週間から数か月と継続することで、エントリーの精度や待つ力が明らかに変わります。
僕自身、毎日のルーティンを繰り返すうちに「焦らないトレード」ができるようになりました。エントリーの数は減りましたが、その分だけ勝率とリスクリワードが改善しています。
結局、トレードは特別な才能よりも日々の継続に支えられるものです。ルーティンを守る積み重ねこそが、安定した成績を導く最大の要因だと言えるでしょう。
まとめ
トレードで勝ち続けるために必要なのは、特別なテクニックよりも日々の準備です。エントリー前のルーティンを徹底することで、感情に左右されない冷静な判断が可能になります。
今回の内容を振り返ると、重要なポイントは以下の通りです。
- 経済指標や要人発言を必ず確認してリスクを避ける
- 休場情報を押さえ、値動きの乏しい日に無理をしない
- X(旧Twitter)で速報を拾い、信頼できる情報源を選別する
- 月足から15分足まで落とし込み、戦うべきポイントを明確化する
- 押し目買いと戻り売りをシナリオ化し、形が出るまで待つ
- 普段使わない根拠は排除し、一貫性を守る
- 朝と夕方に環境認識を更新し、アラートで効率的に待つ
僕が伝えたいのは「準備がすべて」ということです。相場が動いてから考えるのではなく、動く前にシナリオを完成させておく。その積み重ねが、最終的に安定した成績につながっていきます。
今日からでも、自分なりのルーティンを作って実行してみてください。小さな準備の習慣が、大きな結果を生み出す力になるはずです。