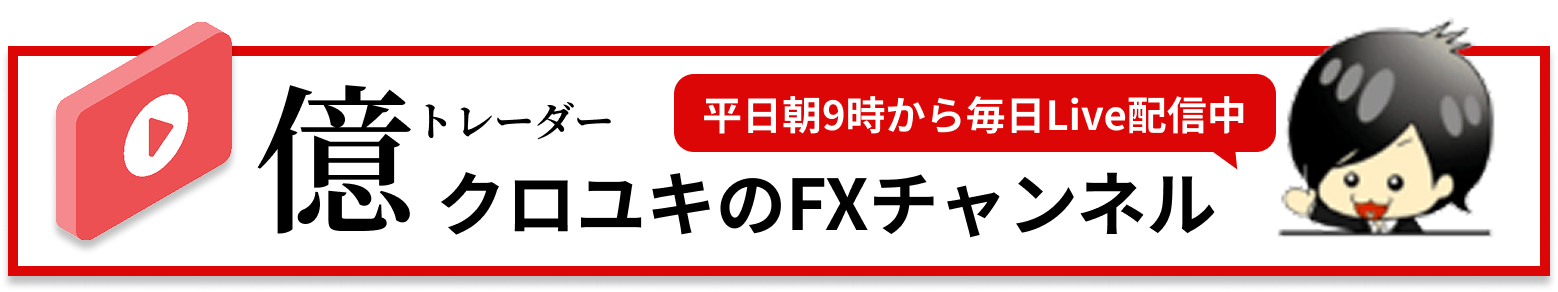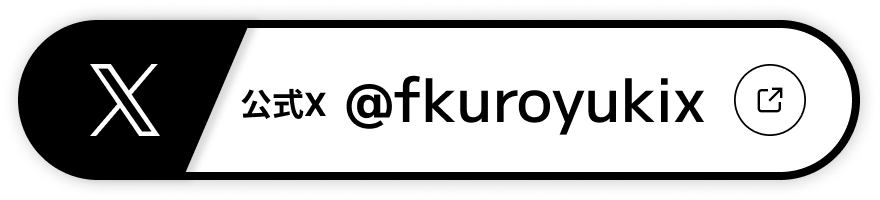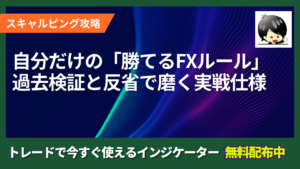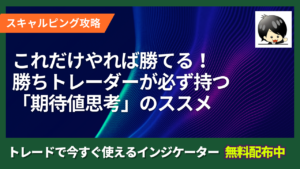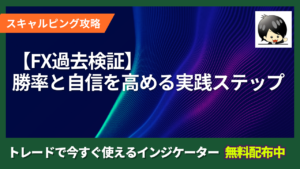2023年を通して振り返ると、僕が最も勝てたのはとにかくシンプルな形に徹した手法でした。複雑なインジケーターや細かい条件を積み重ねるのではなく、チャートの形と値動きの勢いに素直に従うだけで、安定して結果を出すことができたのです。
特にフラッグ(平行チャネル)とダブルトップ/ボトムを組み合わせる手法は、僕自身がライブ配信でも何度も使い、視聴者からの質問にも繰り返し解説してきました。
さらに、高値や安値に到達した際の“停滞からのブレイク”を重ねることで、だましを避けながら初動を取りにいく精度が大きく上がりました。移動平均線で方向を固定し、損切りは二択に統一。時間帯や強い抵抗の有無を加味することで、無駄なエントリーが減り、期待値の積み上げが可能になったと実感しています。
僕も最初は形を「無理やり見よう」として失敗することが多かったのですが、経験を積み重ねる中で、曖昧な場面をスルーする勇気が何よりも大切だと気づきました。
そこで培ったルールと改善をまとめたのが、今回紹介する“シンプルだが最強”の手法です。
以下にその全体像と具体的な運用ポイントを整理しました。
- フラッグ成立は上2点・下2点の反応を最低条件とする
- 上昇チャネルはダブルトップ、下降チャネルはダブルボトムでネック割れ狙い
- 高安ライン到達後の停滞からのブレイクで初動に同乗
- 移動平均線の上下でブレイク方向を限定して逆走を回避
- 損切りは浅めと深めの二択、最低でもリスクリワード1対1を担保
- 3分伸びなければ勢い喪失とみなして縦値撤退
- 近接ラインや上位足の強抵抗が前にある場合は見送り徹底
フラッグとダブルトップを軸にしたシンプルかつ強力な手法の全体像
フラッグとダブルトップ/ボトムの基本原則
トレードで再現性を高めるためには、相場の形を明確に区切る必要があります。その中でも最も効果的だったのが、フラッグとダブルトップ/ボトムの組み合わせです。フラッグはトレンドの流れを示し、ダブルトップやダブルボトムは反転の合図となるため、両者が重なる場面は優位性が高くなります。
たとえば上昇チャネルの上限付近でダブルトップが形成された場合、ネック割れのタイミングはショートの好機となります。逆に下降チャネルではダブルボトムを待ち、ネックを上抜ける場面でロングが狙えます。
この手法の強みは、以下の3点に整理できます。
- トレンド方向と反転シグナルが重なるため、根拠が明確
- ネック割れを基準にすることでエントリーポイントが統一される
- 損切り位置もネック上抜け・下抜けで固定できる
僕自身もこの形を最優先に監視し、曖昧なパターンは見送ることで収支が安定しました。シンプルながら信頼度の高い基本原則です。
平行チャネルの正しい引き方と認識基準
フラッグを成立させるには、チャネルラインの正確な引き方が欠かせません。曖昧なライン取りをしてしまうと、せっかくのパターンも根拠が薄れてしまいます。ポイントは「最低でも上2点・下2点の反応を確認する」ことです。
具体的な手順は次のとおりです。
- 高値同士を結んで下降ラインを引く
- その角度をコピーして安値側に当てる
- 上側はできれば3点以上のヒットがあると理想

画像のように、上2点・下1点しか当たっていない場合はフラッグとしては認識できません。チャネルとしての根拠が弱く、ラインを無理やり当てにいっているだけになってしまいます。この状態でエントリーしても優位性は低く、だましに巻き込まれる可能性が高いです。
修正すべきポイント
- 上下ともに最低2点以上の反応を確認する
- 特に上側は3点以上当たっていると信頼度が高い
- 曖昧なラインは「効いている」と見なさず、見送りを徹底する
僕も検証時に「このくらいなら効いているかも」と入ってしまい、損切りになるケースを何度も経験しました。無理やりラインを見ず、教科書通りの条件が揃うまで待つのが結果的に一番効率的です。
このように正しくラインを引けば、チャネル内の値動きが整理され、エントリー基準も一貫します。逆に少しのヒゲ抜けで「効いている」と無理やり判断するのは避けるべきです。僕も検証時に曖昧なラインを採用して失敗を重ねましたが、思い切ってスルーするようになってから勝率が安定しました。
ライン認識が甘いと手法そのものの再現性が崩れてしまいます。条件を満たしたチャネルにダブルトップ/ボトムが現れる場面こそ、最も信頼できる形です。
2023年で最も勝てたシンプル手法の全体像
2023年を振り返って、僕が最も成果を出せたのは「フラッグ+ダブルトップ/ボトム」のシンプルな組み合わせでした。余計なインジケーターを加えるよりも、形と動きに従った方が勝率も安定度も高まったのです。
この手法の全体像をまとめると、以下の流れになります。
- フラッグを確認し、トレンドの方向性を把握する
- チャネル端でダブルトップ/ボトムを待つ
- ネック割れでエントリー
- 損切りはネック逆抜けに設定
- リスクリワードは最低1対1を確保
さらに、この形は全時間軸で応用できます。僕自身はスキャルピング中心ですが、1時間足や4時間足でも十分に機能します。ただし、日足ベースのトレードはスイング寄りになるため、僕は扱っていません。
シンプルなルールだからこそ迷いが減り、検証や改善もしやすくなります。複雑さを削ぎ落としたこの手法は、2023年に最も稼げた理由の一つだと感じています。
エントリー精度を高めるための具体的条件
フラッグ端で形成されるダブルトップ/ボトムとネック割れエントリー
フラッグ内で値動きが繰り返された後、端に近い位置でダブルトップやダブルボトムが現れると、そこが大きな勝機となります。理由は、チャネルの端は相場参加者が強く意識する抵抗帯となりやすく、そこで二度止められた値動きは反転の可能性が高まるからです。
たとえば上昇チャネルの上限で二度の高値をつけ、ネックラインを下抜けした場面はショートの好機です。逆に下降チャネルでは、二度の安値をつけた後にネックを上抜ければロングが狙えます。僕はこのとき、損切りを必ずネック逆側に設定し、シナリオが崩れたら即撤退できるようにしています。

このパターンを狙うことで、以下のメリットが得られるでしょう。
- ネック割れという明確な条件でエントリーできる
- 損切り位置が固定化されるためリスク管理が容易
- トレンド方向に沿った反転を狙えるため勝率が安定
端で起きた完成形を待つ姿勢が、無駄なトレードを減らし精度を高めるポイントになります。
高安ライン到達後の停滞からのブレイクを狙う判断基準
もう一つ精度を高める鍵が「停滞ブレイク」です。価格がスイング高値や安値に到達した直後に数秒停滞し、その後にブレイク方向へ動き出した場面は強いエントリーチャンスになります。停滞はエネルギーが蓄積されているサインであり、抜けた直後に一気に伸びやすい特徴があるからです。
僕が意識している基準は以下の通りです。
- 停滞時間は最低4秒以上が理想(2秒程度では信頼度が低い)
- 停滞だけでは入らず、必ず抜け方向を確認してからエントリー
- 停滞中の上下ヒゲは許容範囲だが、大きく逆方向に抜けたら見送り
例えば東京時間の午前、スイング高値に到達して4秒以上停滞後に下へ抜けた場面では、ショートで入りやすくなります。僕自身もこのルールを守るようになってから「惜しいから入って負ける」というケースが減り、収支の安定につながりました。
移動平均線を基準にブレイク方向を限定して迷いをなくす
停滞ブレイクを狙う際には、移動平均線を基準に方向を限定するとさらに精度が上がります。移動平均線より価格が上にあるときはロング方向、下にあるときはショート方向のブレイクだけに絞るというものです。
このルールには次のメリットがあります。
- 逆方向のだましブレイクに巻き込まれにくい
- エントリー方向を限定できるため迷いが減る
- 検証が統一されるのでデータの信頼性が高まる
たとえばラインが移動平均線の下側にある場面では、ショートのブレイクだけを狙い、上方向への抜けは完全にスルーします。僕も以前は逆方向の動きに惹かれて入ってしまい負けることが多かったのですが、この基準を取り入れてから連敗が減りました。
シンプルに「MAより上=ロング」「MAより下=ショート」と決めてしまうことで、ブレがなくなり一貫したトレードが可能になります。
損切りと利確を徹底管理するためのルール設計
損切り位置の二択とリスクリワード1対1の確保
損切りをどこに置くかはトレードの成否を大きく左右します。僕が実践しているのは「停滞レンジの端」か「直近スイング外」の二択です。浅い位置に置けば回転率が上がり、深い位置に置けばだましに強くなります。
たとえば停滞下端に2.1pipsの損切りを置くなら、最低でも2.1pips以上の利確を狙います。直近スイング外に置いた場合、損切り幅が4pipsになれば、4pips以上の利幅を必ず確保します。
ポイントは以下の通りです。
- 停滞レンジ端=タイトな管理、損小利小で回転率を重視
- スイング外=余裕を持たせて損大利大、だましに強い
- どちらも最低リスクリワード1対1を守る
二択に絞ることで判断が明確になり、検証データの一貫性も高まるでしょう。
損切り幅と利確幅の調整方法(2pips余裕・1対1以上)
実際のチャートでは、高値や安値に「ほんの少しだけ抜けて戻る」というケースがあります。この場合、損切りをラインぴったりに置くと、最も避けたい“刈られてからの反転”に巻き込まれやすくなります。
僕はこの対策として、損切り幅に数pipsの余裕を持たせています。例えば直近の高値が100.000なら、損切りは100.020〜100.030付近に設定するイメージです。これにより、ヒゲでの損切りを回避しやすくなります。
利確についても同じ考え方です。損切りを2pips広げるなら、利確もその分広げ、常に1対1以上を維持します。これを徹底すれば、一時的なノイズに左右されず、統計的に優位性のある結果を積み上げられます。
3分ルールと縦値撤退を徹底する理由
エントリー後に伸びるかどうかを見極めるには、時間の基準を持つことが有効です。僕は「3分ルール」を取り入れています。具体的には、ブレイク後に3分経っても伸びない場合は、勢いがないと判断して縦値撤退を優先します。
このルールのメリットは以下の通りです。
- 想定シナリオが崩れた場面で損失を避けられる
- 含み益を守り、次のチャンスに備えやすい
- ダラダラとした展開で精神的に消耗しない
僕自身も以前は「まだ伸びるかもしれない」と粘って負けることがありました。しかし3分ルールを徹底してから、建値撤退や微益撤退が増え、損失の拡大を防げるようになりました。
伸びるときは初動ですぐに走ります。走らなければ「今回は違う」と割り切ることが、長期的な安定につながります。
環境認識を取り入れて勝率を底上げする方法
反転ポイントとの重合(水平線・トレンドライン・ピボット等)
エントリーの信頼度を上げるためには、チャートパターンだけでなく環境認識を加えることが大切です。特に有効なのは、もともと反転が起きやすい場所と重なる場面を選ぶことです。
具体的には、以下のポイントが挙げられます。
- 水平線(過去に何度も反応した価格帯)
- トレンドライン(上位足で引いた主要ライン)
- ピボットポイントやオシレーターのシグナル
たとえば4時間足で強く意識される水平線付近で、1分足のフラッグ+ダブルトップが出た場合は、反転確率が格段に高まります。僕自身も、チャートパターン単独よりも、こうした合流ポイントを狙うことで勝率が上がりました。
根拠が重なる場面を優先的に選ぶことで、結果的にトレード回数は減りますが、その分精度の高いエントリーだけを拾えるようになります。
上位足の強い抵抗体がある場面の見送り基準
短期足で完璧な形が出ても、その先に上位足の強い抵抗体が控えていれば、利幅が取れないまま反転してしまう可能性が高いです。このケースでは、エントリーを見送る判断が必要です。
例を挙げると、15分足ではロングの形が整っていても、4時間足で何度も跳ね返された抵抗帯が15pips先にある場合、伸びる余地は限られます。無理にエントリーすれば、狙った利確に届かず反転に巻き込まれるでしょう。
僕も過去に「目先の形が美しい」という理由で飛び込んでしまい、上位足の抵抗に潰される負けを繰り返しました。そこで「上位足に壁があるときは見送る」というルールを設けたところ、不要な損失が減り、トータル収支が安定しました。
環境認識を重視することで、目の前のトレードに飛びつかず、長期的に勝ち続ける基盤が整います。
時間帯リスク(東京9時・中値9:53〜56・イベント急変時)
勝率を高めるには、値動きが乱れやすい時間帯を避けることも欠かせません。特に短期トレードでは、時間帯リスクを理解しておくことが重要です。
注意すべき時間帯は以下の通りです。
- 東京市場オープン直後(9時前後):無意味な上下振れが多い
- 東京中値(9:53〜56):スプレッド拡大や乱高下が発生しやすい
- ロンドンオープン(17時前後):短期的な荒い動きが出やすい
- 突発的なイベント時(要人発言や経済指標):予測不能な値動き
僕自身も、9時直後の動きに飛びついて損切りを連発した経験があります。そのため現在は「9時直後は入らない」「中値付近はスルー」と決めています。また、トランプ前大統領の発言などで突然ボラティリティが急騰した場面もありましたが、そうしたときは一切エントリーしないのが鉄則です。
安定して勝つためには、「入る時間帯」と同じくらい「入らない時間帯」を明確にしておく必要があります。
信頼度を落とすエントリーパターンと避けるべき場面
チャネル中央でのダブル形成は信頼度が低い
フラッグや平行チャネルを利用する際に注意すべきなのは、チャネルの中央付近で現れるダブルトップ/ボトムです。一見すると形は整っていても、チャネル中央は参加者が強く意識しているポイントではないため、反転の信頼度は低くなります。
僕自身も過去に中央付近のダブルトップで入ってみたことがありますが、反発が浅くすぐに逆行して損切りになりました。やはり「端で形成されたダブル」こそが狙うべき形であり、中央はノイズに巻き込まれる可能性が高いです。
エントリーポイントを厳選するためには、チャネル端を徹底的に待つことが重要です。
チャネルを出て大きく戻した後のダブルは勝率低下
もう一つ避けるべきパターンは、チャネルを一度大きく抜けた後に、再び戻してから形成されるダブルトップ/ボトムです。こうした場面ではすでに相場の勢いが弱まり、反転シグナルの信頼度が下がってしまいます。
具体的には、下降チャネルを上にブレイクした後に、再び下方向へ戻してから作られたダブルトップは要注意です。動きがだいぶ遠回りしてから形成されているため、再度大きく伸びる可能性は低くなります。
僕も検証段階でこの形を繰り返し観察しましたが、勝率が明らかに低いと感じました。そのため、こうしたケースは「一見チャンスに見えても見送る」のが正解です。
近接する二本ラインがある場面は最深部のみを採用
ラインが近接して存在する場合は、どちらを基準にするか迷いやすいです。特にフラッグや水平線で2本のラインが狭い範囲にあると、エントリーの判断がぶれがちになります。
僕が徹底しているのは「最も深い方のラインだけを見る」ことです。たとえば上昇局面で直近に2本の抵抗線がある場合、浅い方ではなく、より上にある強い抵抗だけを基準にします。浅い方でのブレイクを狙うと、すぐに深いラインで反発されて負けやすいからです。
この考え方はブレイク狙いにおいて特に重要です。抵抗が連続している場面では、手前のラインをスルーして最深部を待つだけで、だましの回避率が大幅に高まります。
実践トレードで意識すべき注意点と上達のコツ
無理やりラインやパターンを見ない重要性
トレードを始めたばかりの頃に多い失敗は「無理やりラインを当てにいく」ことです。たとえば、わずかに触れただけの点を2点と数えたり、明らかに機能していない部分を「効いている」と解釈してしまうケースです。こうした裁量の甘さは、再現性を崩し、検証結果を不正確にしてしまいます。
僕自身も経験上、「効いていそうだから」と無理やり見てエントリーすると、統計的に不利な場所に入ってしまうことが多くありました。勝てるときもありますが、長期的に見ると収支は安定しません。
結局のところ、きれいに効いている場面を選別して待つことが、勝ち続けるための近道です。迷うなら「見送り」を正解にする意識が大切です。
停滞秒数の基準(4秒以上を理想・2秒は弱い)
停滞ブレイクを狙う際は「停滞の長さ」も重要な判断基準になります。僕は最低でも4秒以上の停滞を理想としています。2秒程度ではレンジの蓄積が弱く、抜けても伸びないことが多いからです。
具体的には以下の基準を持っています。
- 4秒以上:信頼度が高く、エントリー候補
- 2〜3秒:一応可能だが、勝率は下がる
- 1秒未満:停滞とは見なさず、対象外
このルールを設けてから、不要なだましに巻き込まれる回数が大幅に減りました。停滞秒数を定量化することで、主観的な判断を避け、トレードの精度が向上します。
差し値よりも成行決済を基本とする理由
スキャルピングや短期トレードでは、利確・損切りを差し値で固定するのが難しい場面があります。証券会社によっては「現在値から一定pips以上離れていないと指値を置けない」という制約があるためです。
僕も実際に差し値を置こうとして間に合わず、結果的に取りこぼしたことが何度もあります。そのため現在は成行決済を前提とし、常にチャートを見ながら即時で対応するスタイルに切り替えました。
もちろん成行には判断の素早さが求められますが、短期ではむしろそれが合理的です。停滞ブレイクのような一瞬の勝負では、成行でスパッと抜ける方が安定します。
形を曖昧にせず“教科書通り”を優先する
トレードでは「本来なら見送りの場面」を無理に解釈して入ってしまうことが多いです。しかし、勝てる人と負ける人の差はここで分かれます。僕が意識しているのは「教科書通りの形だけを狙う」ことです。
たとえばフラッグであれば上2点・下2点が明確に反応しているものだけを採用し、少し曖昧なラインは排除します。停滞ブレイクも、秒数や方向性が基準を満たさなければスルーします。
この習慣を徹底すると、トレード回数は一時的に減りますが、勝率が上がり無駄な損失が減ります。長期的には資産曲線が滑らかに伸びていき、安心して続けられる環境が整うでしょう。
学習効率を高める環境とフィードバックの活用法
リアルタイム相場での検証と修正の重要性
トレードの上達には、リアルタイムの相場で実際に試し、結果を振り返る作業が欠かせません。書籍や動画で学んだ手法も、リアルタイムで使ってみると「ここは入ってはいけない」「思ったより反応が弱い」など、机上の学びとは違う部分が見えてきます。
僕自身も録画やスクリーンショットを残し、停滞秒数や初動の伸び方を記録してきました。後から振り返ることで、自分の判断が正しかったかどうかを客観的に確認できるようになり、修正点が明確になります。
結局、相場は常に生き物のように変化します。だからこそ「リアルタイムで検証→振り返り→改善」の流れを回すことが、学習効率を大きく高めるのです。
ライブ配信やX(旧Twitter)での質問と添削活用
独学だけでは気づけないのが「自分の思い込み」です。僕もそうでしたが、本人は正しくやっているつもりでも、第三者から見ると「そのラインは無理やり」「そこは入ってはいけない」と明確にズレているケースが多々あります。
そのため僕は、ライブ配信やX(旧Twitter)を活用して質問を受け付けています。例えば「フラッグとダブルトップで入ったが負けた、判断は合っていたか?」と聞いてもらえれば、僕の視点で添削し、修正すべき点を伝えています。
このように、外部からのフィードバックを受けられる環境を持つことは、学習スピードを飛躍的に高める近道です。
セミナーで得られる内容(スキャル2種・マインド・仲間づくり)
さらに効率よく学ぶ方法のひとつが、セミナーを通じた体系的な学習です。僕が実施しているセミナーでは、以下の内容を中心に解説しています。
- パターンで入るスキャルピング手法
- プライスアクションで入るスキャルピング手法
- それらを使いこなすためのマインドセット
- 参加者同士での情報共有や仲間づくり
特に仲間の存在は大きく、自分では気づけないエラーを指摘し合えたり、成績に伸び悩む時もモチベーションを保てます。僕自身、チームでの取り組みから得られる効果を強く感じています。
セミナー参加後に繰り返し学べる動画視聴とフィードバック環境
セミナーは一度聞いただけでは理解が漏れる部分が出てしまいます。そのため、参加者には後日動画を配布し、繰り返し学べる環境を提供しています。何度も見返すことで、曖昧だった部分を補強でき、実践に落とし込みやすくなるでしょう。
さらに、日々のライブ配信ではリアル相場を用いたフィードバックを行っています。セミナーで学んだ内容を、実際のマーケットでどう活かすかを確認できるので、知識と実践のギャップを埋めやすくなります。
僕が意識しているのは「学んで終わりにせず、繰り返し触れて定着させる」ことです。この仕組みを活用すれば、短期間で手法を自分のものにしやすくなります。
まとめ
今回ご紹介した内容は、複雑なインジケーターを排除し、フラッグとダブルトップ/ボトム、そして停滞ブレイクに絞ったシンプルな手法です。僕自身も2023年を通じて最も成果を出せたのは、この形に徹底して向き合ったからでした。
要点を整理すると次の通りです。
- フラッグは上2点・下2点以上の反応を確認して認識する
- チャネル端で形成されるダブルトップ/ボトムを狙い、ネック割れで入る
- 高値安値に到達後の停滞からのブレイクは強いエントリー条件
- 移動平均線を基準に方向を限定し、逆方向のブレイクは見送る
- 損切りは停滞端か直近スイング外の二択とし、最低リスクリワード1対1を担保
- ブレイク後3分伸びなければ縦値撤退に切り替え、損失を防ぐ
- 上位足の強抵抗や時間帯リスク(東京9時・中値前後・イベント急変)は必ず考慮する
シンプルに見えても、ルールを守るには一貫した姿勢が求められます。無理やり形を探さず、教科書通りの条件が揃った場面だけに絞ることで、期待値の積み上げが可能になります。
僕も最初は曖昧な場面に飛び込み失敗を繰り返しましたが、ルールを徹底してから収支が安定しました。ぜひ今回のまとめを参考に、自分のトレードに組み込んでみてください。